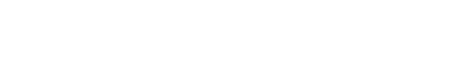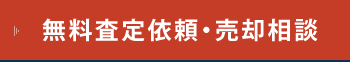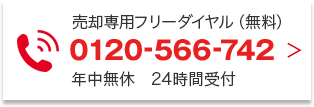不動産売却時にかかる税金とは?種類や計算方法、活用できる特例を解説
不動産売却に関する基礎知識 更新日付:2025.12.18

2025年12月時点の情報及び税制に基づいて記載しております。
不動産の売却時には、どのような税金がかかるのでしょうか。売却計画を立てる上では、細かな税金の種類や計算方法を把握しておくことも重要です。
この記事では、不動産売却時に発生する税金の種類とそれぞれの計算方法、活用できる特例などをわかりやすく解説します。不動産の売却をご検討中の方は、この機会にぜひチェックしてみてください。
目次
不動産売却にかかる税金の種類

不動産の売却を検討する際は、手続きにともなって発生する税金にも目を向けておく必要があります。ここではまず、不動産売却時にかかる税金の種類を全体像で確認しておきましょう。
| 税金の種類 | 税率・税額 | 課税されるタイミング |
|---|---|---|
| 印紙税 | 数千~数万円 | 売買契約書の作成時 |
| 登録免許税 | 1,000円/1件 | 抵当権抹消登記時(原則決済日) |
| 消費税 | 10% | 売買契約の成立後(仲介手数料に対して課税) |
| 譲渡所得税・復興特別所得税 | 所有期間に応じて変動 | 翌年の確定申告時 |
| 住民税 | 所有期間に応じて変動 | 翌年の確定申告後 |
上記のように、不動産を売却する際はさまざまな税金がかかります。具体的な金額のイメージを持つための計算例をまとめると次の通りです。
| 物件の所有期間 | 5年以下(短期譲渡所得) | 5年超(長期譲渡所得) |
|---|---|---|
| 譲渡所得税・復興特別所得税・住民税を合わせた税率 | 39.63% | 20.315% |
| 譲渡所得税・復興特別所得税・住民税の税額 | (売却価格 – 取得費 – 諸費用)×税率(39.63%) =(4,000万円-3,000万円-300万円)×39.63% =277万4,100円 |
(売却価格 – 取得費 – 諸費用)×税率(20.315%) =(4,000万円-3,000万円-300万円)×20.315% =142万2,050円 |
物件の取得費3,000万円、売却価格4,000万円、売却時の諸費用・取得費300万円の設定で試算。印紙税・登録免許税・仲介手数料にかかる消費税は、売却時の諸費用・取得費に含まれる。
※物件の所有期間は、売却した年の1月1日時点で計算する。
物件の所有期間によって税率は異なるため、どのタイミングで物件を売却するかの判断材料となるでしょう。また、一定の条件を満たせば、後述する税制上の特例を受けられるケースがあるので、詳しく確認しておくことが大切です。
印紙税
印紙税とは、「課税文書」と呼ばれる特定の契約書などを交わす際に発生する税金のことです。不動産の売却時に交わす「不動産売買契約書」も課税文書の一種であり、取り交わす際には取引金額に応じた印紙税が発生します。
印紙税は書面に収入印紙を貼り付け、消印をすることで納付したものと見なされます。なお、「不動産売買契約書」については、令和9年(2027年)3月31日まで、以下の表のように軽減措置が適用されます。
| 契約金額 | 通常の税額 | 軽減後税額 |
|---|---|---|
| 10万円超 50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超 100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超 5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円超 10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円超 50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
(出典:国税庁『「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について』)
登録免許税
登録免許税とは、登記の手続きを行う際にかかる税金のことです。通常、不動産を売却するだけであれば発生しませんが、住宅ローンを組んで購入していて、完済していない、または完済していても抹消登記をしていない物件を売る場合は「抵当権抹消登記」という手続きが必要となります。
住宅ローンを完済している場合、すでに返済の義務自体はなくなっていますが、登記上には金融機関の抵当権が設定されたままになっています。そのままではさまざまなトラブルの原因となるため、売却する前には抵当権抹消登記という手続きをし、権利関係をクリアにしなければなりません。
このとき、「不動産1件あたりにつき1,000円」の登録免許税が発生します。例えば、一戸建てを売る場合は、土地と建物それぞれで手続きを行う必要があるため、合計2,000円の登録免許税がかかります。
マンションも土地と区分所有している建物(部屋)を別個の不動産として取り扱うため、考え方は一戸建てと同じです。なお、複数の筆で構成されている土地に建物が建っている場合は、土地の筆数分の費用がかかるので注意が必要です。
消費税
不動産会社を通じて売却を行う際には、成功報酬として仲介手数料がかかります。仲介手数料はサービス(役務)の対価となるため、消費税の対象として通常のサービスと同じように10%の税率が適用されます。
なお、仲介手数料は法律によって上限が決められており、取引金額が400万円を超える場合は、「取引金額×3%+6万円+消費税」が上限金額です。例えば、3,000万円で売却が成立した場合、仲介手数料の上限は105万6,000円(税込)となります。
所得税・住民税
不動産を売却して利益が出たときは、その譲渡益に対して所得税・住民税がかかります。ただし、譲渡で発生した所得に対して、自動的に課税されるものではないため、翌年の確定申告において、自ら申告・納付しなければならない点に注意が必要です。
また、2037年までは所得税と併せて2.1%の復興特別所得税も課税されるため、上乗せして計算する必要があります。
そして、確定申告の内容に基づき、その年の6月から住民税の納付が始まります。譲渡で得た利益に対して課される所得税や住民税は、一般的に「譲渡所得税」とも呼ばれており、その他の税金と比べて計算方法が複雑な点にも注意が必要です。
ここからは、譲渡所得税の仕組みや計算方法について、詳しく見ていきましょう。
不動産の譲渡所得税・住民税の計算方法

譲渡所得税(+復興特別所得税)・住民税は、おおまかに次の3つの手順で計算します。ここでは、各ステップの具体的な内容や注意点について解説します。
- ステップ1:譲渡所得を計算する
- ステップ2:課税譲渡所得を割り出す
- ステップ3:所有期間に応じた税率をかける
ステップ1:譲渡所得を計算する
譲渡所得税・住民税は、利益(譲渡所得)に対して課される税金です。そのため、まずは不動産売却によって、譲渡所得がどのくらい生まれたのかを正しく計算しなければなりません。
譲渡所得の計算方法は次の通りです。
譲渡所得=物件の売却金額-(売却時の諸費用+取得費)
つまり、譲渡所得は、売却できた金額から「売るためにかかったコスト」と「購入・取得するためにかかったコスト」を差し引いて求めるということです。
売却金額に含まれるもの
売却金額は、不動産の売却代金に固定資産税・都市計画税の清算金を加算して計算します。固定資産税・都市計画税の清算金とは、年の途中で不動産を売却したときに、買主に払い戻してもらうお金のことです。
固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課税される仕組みとなっています。そのため、年の途中で不動産の引渡しが行われた場合、売主は年末までの日数分の税金を余計に負担することとなってしまいます。
そのため、不動産売買時には、あらかじめ売主が払い込んでいた1年分の固定資産税・都市計画税から、年末までの日数で日割り計算した分を買主が精算する慣習があるのです。譲渡所得の計算においては、買主に精算してもらった固定資産税・都市計画税を売却金額に組み込む必要があるので注意しましょう。
売却時の諸費用に含まれるもの
売却時の諸費用(譲渡費用)には、次のようなものがあります。
- 仲介手数料
- 印紙税(売主が負担したもの)
- 土地を売るために建物を取り壊した場合の解体費用や建物の減価償却費
- すでに売買契約を締結した不動産をより有利な条件で売るために支払った違約金
- 貸家を売るために、借家人に支払った立ち退き料 など
マイホームを売却する場合は、仲介手数料と印紙税が主な譲渡費用となります。譲渡所得の計算時には、これらの経費を売却金額から差し引けるので、忘れずにチェックしましょう。
取得費に含まれるもの
取得費とは、不動産を取得するためにかかった費用のことであり、次のようなものが含まれます。
- 土地や建物の購入代金
- 建物の建築費
- 設備費、改良費
- 購入時の印紙税、不動産取得税、登録免許税、登記費用
- 土地の造成費、測量費 など
マイホームを売却する場合は、土地や建物の購入・建築費やリフォーム費用、購入時にかかった税金・手数料などを取得費として差し引けます。ただし、建物の取得費については、「減価償却費相当額を差し引かなければならない」点に注意が必要です。
建物は経年劣化によって価値が目減りしていくため、売主は築年数分だけ建物の価値を消費したと考えるのが自然です。購入時の金額をまるごと取得費に計上するのは、税法上適切な処理とは言えないため、消耗した価値を差し引くために減価償却費の控除が必要となるのです。
建物の減価償却費は、以下の計算式で求めることができます。
減価償却費=取得価額×0.9×償却率×経過年数(※)
※1年未満の端数は、6ヶ月以上なら1年として扱い、6ヶ月未満は切り捨てる
償却率は建物の種類や用途によって異なり、一般的な木造一戸建ての住居であれば0.031、鉄筋コンクリート造マンションは0.015です。例えば、建物価格4,000万円で購入した木造一戸建てを20年後に売却するなら、減価償却費は「4,000万円×0.9×0.031×20=2,232万円」となります。
その他の構造の建物や、事業用の建物についても、国税庁などのホームページで簡単に調べることができます。
(参考:国税庁『「減価償却費」の計算について』)
なお、正確な取得費がわからない場合は、「売却金額×5%」相当額を「概算取得費」として計上することも可能です。相続をした場合などで取得費がわからないケース、実際の取得費が売却金額の5%を下回るケースでは、概算取得費を使うとよいでしょう。
ステップ2:課税譲渡所得を割り出す
「課税譲渡所得」とは、実際に課税対象となる所得のことです。譲渡所得を割り出した後は、以下の計算式で課税譲渡所得を求めましょう。
課税譲渡所得=譲渡所得-特別控除額
特別控除の種類は後ほど詳しくご紹介しますが、代表的なものとしては、「居住用財産の売却時の3,000万円の特別控除」があります。マイホームの売却では、多くのケースでこの特例を利用できるため、譲渡所得から3,000万円を控除した結果、「課税譲渡所得がゼロ」となることもめずらしくありません。
ステップ3:所有期間に応じた税率をかける
課税譲渡所得を割り出したら、最後に所得税率をかけて税額を計算します。譲渡所得の税率は、売却した物件の所有期間によって、以下のように区分されています。
| 種類 | 条件 | 税率 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 所有期間 5年以下 |
39.63% | ・所得税+復興特別所得税:30.63% ・住民税:9% |
| 長期譲渡所得 | 所有期間 5年超 |
20.315% | ・所得税+復興特別所得税:15.315% ・住民税:5% |
※所有期間の計算は、「売却した年の1月1日時点まで」の経過年数を対象とする。
上記のように、短期譲渡所得と長期譲渡所得では税率に大きな違いがあります。この差は、投機目的での短期土地売買を抑制するために設けられたものであり、どちらが適用されるかによって税額が大きく変わってきます。
また、所有期間の計算については、売却した時点ではなく、その年の1月1日までさかのぼる点にも注意が必要です。例えば、2020年8月に取得した不動産を2025年12月31日に売却する場合、実際には所有期間が5年を超えていても、2025年1月1日が基準となるため、計算上は5年に達したことにはなりません。
つまり、売却時期によっては短期譲渡所得と見なされ、高い方の税率が適用されてしまうということです。ちなみに、このケースで長期譲渡所得の税率を適用させたい場合は、2026年まで売却を見送る必要があります。
不動産売却での節税に利用できる4つの特例

不動産売却時にかかる税金のうち、節税できる可能性があるのは「譲渡所得税」です。譲渡所得税の計算においては、状況に応じてさまざまな特例を活用できます。
ここでは、節税につながる4つの特例をご紹介します。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
居住用財産とはいわゆるマイホームのことです。マイホームの売却時には、一定の条件を満たすことで、譲渡所得から3,000万円を控除できるようになります。主な条件は次の通りです。
- マイホームを売却する
- すでに居住していない場合は、3年が経過する年の12月31日までに売却する
- 売却の年と前年、及び前々年に本特例やマイホームの買い換えや交換の特例などを利用していない
- 親子や夫婦などの「特別の関係がある人」に売ったものでない
(出典:国税庁『No.3302 マイホームを売ったときの特例』)
細かな条件は設定されていますが、自ら住んでいた家を売るのであれば、ほとんどの場合に適用できます。控除の金額も大きいため、マイホームの売却では優先的に利用したい制度と言えるでしょう。
ただし、この特例は住宅ローン控除と併用できない点に注意が必要です。自宅の買い換えを目的に売却する場合は、新しく買う住宅で住宅ローン控除が利用できなくなる点を踏まえ、どちらが有利なのかをしっかり検討しておくことをおすすめします。
所有期間10年超のマイホームを売却した場合の軽減税率
所有期間が10年を超えるマイホームを売却する際には、通常の長期譲渡所得よりもさらに低い税率が適用される特例があります。具体的には、課税譲渡所得のうち、この6,000万円以下の部分に対しての税率が14.21%に軽減されます。
なお、この特例は前述した3,000万円の特別控除との併用が可能です。
相続空き家を売却したときの3,000万円の特別控除の特例
相続した空き家を売却したとき、一定の要件を満たしていれば、譲渡所得に対して最大で3,000万円までの特別控除を適用させることができます。要件は以下のようにやや複雑であるため、利用する際は税理士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
土地・建物に関する要件
- 1.昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された建物であること
- 2.区分所有建物登記がされていない建物であること
- 3.相続開始の直前まで被相続人以外が居住していなかったこと(被相続人が老人ホーム等に入居していた場合などは例外)
特例の適用を受けるための主な要件
- 1.相続または遺贈で空き家と土地をともに取得したものであること
- 2.売却代金が1億円以下であること
- 3.建物付きの場合は売却日までに家屋全部を取り壊す、あるいは翌年の2月15日までに耐震基準を満たすリフォーム工事を行うこと
- 4.相続時から売却時まで事業用・賃貸用・居住用として使用されていないこと
- 5.他の特例の適用を受けていないこと
- 6.売却先が親子や夫婦などの「特別の関係がある人」でないこと
(出典:国税庁『No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例』)
また、この特例は売却日が「令和9年(2027年)12月31日まで」の時限的な措置となっている点にも注意が必要です。
特定の居住用財産の買い換えの特例
下記は、特定の条件を満たした状態でマイホームの買い換えを行う際に、譲渡所得税の課税を将来に繰り延べられる特例の主な要件です。
- 1.売却するマイホームと購入するマイホームがどちらも日本国内にあること
- 2.居住期間が10年以上あり、売った年の1月1日において家屋や敷地の所有時間がともに10年を超えること
- 3.売却先が親子や夫婦などの「特別の関係がある人」でないこと
- 4.売却代金が1億円以下であること
- 5.売却した年の前年から翌年までの3年の間にマイホームを買い換え、売った年の翌年の12月31日までに住むこと(翌年に購入する場合は、翌々年の12月31日まで)
- 6.買い換えるマイホームに関する特定の要件を満たすこと
(出典:国税庁『No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例』)
買い換え特例については、売却する物件だけでなく、購入する物件に関する条件も満たさなければなりません。また、売却日が「令和7年(2025年)12月31日まで」の時限的な特例となっているため、利用を検討している場合は期限にも注意が必要です。
譲渡「損失」が出た場合に利用できる制度

今回ご紹介したように、不動産を売却して譲渡損失が出た場合には、特に確定申告をする必要はありません。しかし、申告をすることで、「損益通算」を利用できるようになります。
損益通算とは、所得の黒字と赤字を相殺できる仕組みです。基本的に不動産の譲渡所得の損失については、その他の所得と相殺することはできません。
しかし、一定の要件を満たしたマイホームの譲渡による損失は、その年の事業所得や給与所得とも損益通算できるという特例があります。そのうちの1つは「特定のマイホームの譲渡損失と損益通算及び繰越控除の特例」と呼ばれ、住宅ローンが残っていて長期譲渡所得に該当する場合のマイホームの譲渡損失を、事業所得や給与所得と相殺できる仕組みです。
また、買い換えを行う場合は、「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を利用することもできます。これは、マイホームの買い換えで譲渡損失が出たときに、一定の条件を満たすことで損益通算が行える特例です。
いずれの特例も、損益通算で控除しきれなかった部分を、翌年以後3年間にわたって繰越控除することができます。利用すれば給与所得の所得税軽減につながるため、譲渡損失が出た場合も、確定申告を行うことが大切です。
(出典:国税庁『No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)』)
(出典:国税庁『No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)』)
相続した不動産を売却するときのルール

相続した不動産を売るときは、自ら購入した不動産と異なり注意しなければならないポイントがいくつかあります。最後に、相続した不動産を売却するときの基本的なルールをご紹介します。
取得費は前の所有者のものが引き継がれる
贈与や相続で取得した不動産については、前の所有者の取得費が引き継がれます。そのため、売却する際は、できるだけ正確な取得費を調べておくことが大切です。
取得費の計算には、相続した時点や売却を考えている現在の価額は反映されません。あくまで「前の所有者が取得した当時の価格」が基準となるため、計算を行う際はこの点に注意しましょう。
また、相続した不動産の売却においては、相続時に支払った登記費用や不動産取得税なども取得費に含まれます。
相続税の一部は取得費に加算できる可能性がある
相続税は原則として取得費に含まれませんが、一定の要件を満たすことで、取得費への加算が認められます。利用するための条件は次の通りです。
- 相続や遺贈により財産を取得した者であること
- その財産を取得した人に相続税が課税されていること
- 相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること
(出典:国税庁『No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例』)
条件は比較的にシンプルで、基本的には相続した翌日から3年以内に売却すれば、この特例は利用可能です。
所有期間も引き継がれる
相続・贈与された不動産は、所有期間も前の所有者から引き継ぐこととなっています。例えば、自身が相続後に所有している期間が5年未満であっても、前の所有者の所有期間を加えて5年以上になれば、長期譲渡所得として扱うことが可能です。
不動産売却の税金は、所有期間によって条件が変わることが多いため、前の所有者が取得した時期も正確に把握しておくとよいでしょう。
まとめ

不動産の売却を検討する際は、どのような税金がどのくらい発生するのかを把握しておくことが大切です。特に売却利益が出たときに生じる所得税や住民税は、計算が複雑であるため、1つずつ丁寧に理解を進めていく必要があります。
また、税金の負担額は、不動産の売却金額によって大きく異なります。どのくらいで売れるのか、目安を把握するためにも、早い段階で不動産売却査定を行うとよいでしょう。
住友不動産ステップでは、最短60秒ですぐにわかる「ステップAI査定」や、営業担当者が現地へ足を運んで正確な査定を行う「無料訪問査定」をご用意しております。「電話番号を入力したくない」「とりあえず売却額目安をすぐに知りたい」という方は、「ステップAI査定」がおすすめです。
また、「詳しい売却可能額を知りたい」「管理状況や周辺環境も踏まえた査定額が知りたい」という方は、ぜひ訪問査定をご利用ください。
関連記事
他にも詳しく知りたい方は以下の記事も参考になります。
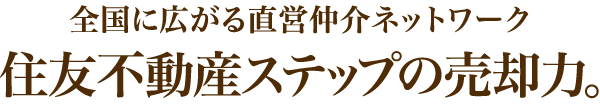
-
広告戦略からアフターフォローまで
マンツーマン営業体制 -

お問い合わせ時から、買主募集の広告戦略、ご契約、お引き渡し、アフターフォローまで、一貫した「マンツーマンの営業体制」により、お取引を責任を持って担当します。
-
地域に密着した営業ネットワーク
全国172営業センター -

全国に広がる172営業センターの地元に精通した営業担当者だからこそ、地域に密着したお取引を行うことが可能です。
※2026年1月1日時点
-
多彩なメディアを活用した
広告ネットワーク -

自社サイトの他、SUUMO・アットホームなど各種提携サイト※へ物件広告を行います。
※物件により掲載条件があります。
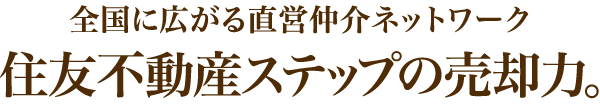
-
広告戦略からアフターフォローまで
マンツーマン営業体制 -
お問い合わせ時から、買主募集の広告戦略、ご契約、お引き渡し、アフターフォローまで、一貫した「マンツーマンの営業体制」により、お取引を責任を持ってご担当します。
-
地域に密着した営業ネットワーク
全国172営業センター -
全国に広がる172営業センターの地元に精通した営業担当者だからこそ、地域に密着したお取引を行うことが可能です。
※2026年1月1日時点
-
多彩なメディアを活用した
広告ネットワーク -
自社サイトの他、SUUMO・アットホームなど各種提携サイト※へ物件広告を行います。
※物件により掲載条件があります。
お気軽にご相談ください。
住み替えを検討している
税金や費用を知りたい
オークション形式の不動産売買をしたい
相続・空き地・空き家相談
売却・賃貸どちらが良い?
収益物件を組み替えたい
不動産売却お役立ちガイド
-
結婚、転勤、退職など、ライフステージの変化にあわせて住まいも変わるもの。その際に持ち家をどうすればよいかの不安や疑問にお答えします。
-
不動産取引の会話や文章によく出てくる専門用語を五十音順に掲載しました。辞書としてご活用ください。
-
住まいにまつわるさまざまな税金の知識を、身近なケースに即してわかりやすいQ&A形式でまとめました。初めての方にもわかりやすいよう、基本的な税制について紹介します。
-
ご所有のマンションなどを売却する際、売却検討や査定から引渡しまでの流れとポイントを説明します。
-
不動産売買時のよくあるご質問をQ&A形式でご紹介します。不動産売買について疑問がある方はこちらからご確認下さい。
-
はじめてマンションを売却する方は必見。売却までの流れの他、準備するべきポイントなどをご説明します。
-
一般の土地取引の指標ともなっている公示地価・基準地価を確認できます。(当社営業エリアのみ掲載)