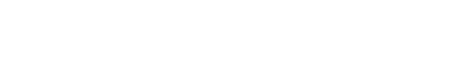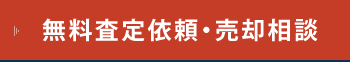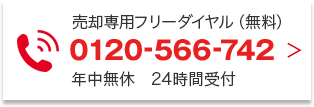共有名義の不動産売却のポイントは?売却の流れや注意点を解説
不動産売却に関する基礎知識 更新日付:2025.12.18

2025年12月時点の情報及び税制に基づいて記載しております。
共有名義の不動産を売却する際は、どのような点に気をつければよいのでしょうか。この記事では、共有の基本的な仕組みや、共有名義の不動産を売却するときの流れを詳しく解説します。
また、2025年5月時点の法制度に基づいた、共有名義の不動産で起こりやすいトラブルと、スムーズに売却手続きを進めるための注意点についてもご紹介します。共有名義の不動産売却をお考えの方は、ぜひご覧ください。
目次
不動産の共有名義とは

共有名義の不動産は、単独名義の不動産とは異なり、売却などの手続きが複雑化しやすいのが特徴です。ここではまず、「共有」とはどのような状態を指すのか、基本的な仕組みを確認しておきましょう。
共有とは
共有とは、民法第一編第三章第三節(第249条~第264条)で定められた、車や建物のように物理的に分割できないものを複数人で共同所有する形態を指します。例えば、夫婦が共同で住宅ローンを組んで一戸建てを購入した場合、土地と建物は夫婦で共有することになります。
1人で所有する単独所有と異なり、共有ではそれぞれに「共有持分」と呼ばれる権利が認められるのが特徴です。また、共有持分は必ずしも等分されるわけではなく、出資した金額や相続時の割合によって異なります。
(出典:e-Gov『民法第三節 共有』)
共有者に認められた3つの権利
共有者に認められる主な権利は、「保存」「管理」「変更(処分)」の3つです。
| 行為 | 具体的な内容 | 条件 |
|---|---|---|
| 保存 | ・所有権移転登記 ・修繕 など |
単独で実行可能 |
| 管理 | ・短期での賃貸借契約 ・賃料の減額 ・分筆、合筆 |
持分割合の過半数の合意が必要 |
| 変更(処分) | ・売却 ・贈与 ・長期の賃貸借契約 ・増改築 |
全員の合意が必要 |
このうち単独で実行できるのは保存行為、あるいは持分を過半数持っている場合の管理行為のみであり、変更行為は他の共有者の合意がなければ認められません。不動産の売却は変更行為に該当するため、共有者全員の合意がなければ実行できない点に注意が必要です。
ただし、「自身の共有持分のみの売却」であれば、単独でも実行できる場合もあります。そのため、共有不動産の売却には、後述するようにさまざまな選択肢が存在します。
共有名義の不動産を売却する際の4つの選択肢

共有名義の不動産売却には、大きく分けて4つの方法があります。
共有者全員の合意を得て売却する
共有者全員が売却に賛成している場合は、合意をまとめればそのまま手続きを進めることができます。不動産は単独名義のものと同様、シンプルに1つの物件として市場に出すことができるため、資産価値を維持したまま買い手を見つけやすくなるのがメリットです。
また、売却によって得られた現金は、持分に応じて共有者間での協議のうえ分配されるため、処分後の扱いが明快になりやすいという利点もあります。共有者が少なく連絡がとりやすい場合や、売却の意思を確認しやすい状況であれば、全員での合意を目指すのが理想と言えるでしょう。
ただし、共有名義の不動産を売却する場合は、原則決済時に全員が立ち会う必要があるなど、通常よりも手間がかかります。そのため、事前の話し合いで代表者を決めておき、手続きはその代表者に委任するのが一般的です。
また、持分割合に応じない分配をする場合、取り分が少ない共有者から多い共有者への「贈与」とみなされて贈与税が課される可能性があるため、慎重に協議する必要があります。
自身の持分を「他の共有者に」買い取ってもらう
先にも述べたように、自身の共有持分のみであれば、自分1人でも売却を進めることができます。全員の合意が得られにくく、それでも共有持分を手放したいという場合は、他の共有者に買い取ってもらうことも可能です。
仮にすべての共有持分を1人が買い取れば、単独名義の不動産として取り扱えるようになるため、将来的な運用・売却がしやすくなります。買い取る側にとっても大きなメリットがあるので、共有者との関係性が良好であれば、スムーズな話し合いが期待できるでしょう。
ただし、相場よりも極端に安い価格で取引が行われると、売り手から買い手への「贈与」とみなされて贈与税が課される可能性があります。話し合いをまとめる際は、条件が相場から乖離しすぎないように注意しましょう。
自身の持分を「第三者に」買い取ってもらう
共有持分については、共有者以外の第三者に売却することも法的に認められています。ただし、第三者が共有持分のみを取得しても、自由に使ったり売却したりすることはできません。
また、他の共有者との間でトラブルになるリスクもあるため、売り先は基本的に不動産の共有持分を専門に買い取る会社などがメインとなります。取り扱いの難しさを踏まえると、買取価格は相場から大幅に下がる可能性もあるため、資産運用の方法としてはあまり望ましくない結果になる可能性があります。
更地で面積が大きな土地は文筆してから売却することも
共有している不動産は、「分筆」してから売却することも可能です。分筆とは、登記上で単一とされている土地を複数に分ける行為を指します。
共有持分に応じて分筆をすれば、各々が分筆後の土地の単独所有者となるため、売却も自由に行えます。また、共有している土地の分筆に関するルールは、2023年の民法改正によって大きく変更されました。
従来は、分筆登記をするために共有者全員の合意が必要とされていましたが、改正によって「持分の過半数の合意」で申請できるようになっています。手続きの条件が緩和されたことで、分筆も土地の共有持分を売却する有力な方法になったと言えるでしょう。
ただし、分筆を行う際は正確な測量が必要となるため、専門家である土地家屋調査士に手続きを依頼するのが基本です。測量や登記手続きの費用が発生するため、売却価格と売却費用のバランスを慎重に見極めることが大切です。
共有名義の不動産を売却する際の流れ

ここからは、共有名義の不動産を共有者全員の合意を得て売却する場合の流れについて、以下の5つのステップに分けて解説します。
- ステップ1:共有者間で合意形成を図る
- ステップ2:必要書類を準備する
- ステップ3:売却活動を進める
- ステップ4:収益を分配する
- ステップ5:税金の申告と納付を済ませる
ステップ1:共有者間で合意形成を図る
まずは全体の合意を得るために、共有者全員の所在を確認します。共有が開始してから長い年月が経過している場合は、すでに相続などで権利が複雑化している可能性もあります。
共有者の情報は、法務局で取得できる登記事項証明書(登記簿謄本)で確認できますが、相続登記等がされておらず、後から新たな共有者が見つかれば、その時点で手続きがやり直しになってしまう恐れがあるので、権利関係は正確に把握する必要があります。
登記事項証明書には、持分割合も記載されているので、同時に確認しておくとよいでしょう。共有者を把握したら、それぞれに話し合いを求める意思を伝え、合意形成の場を設定します。
遠方の共有者がいる場合は、必要に応じてメールやグループチャット、ビデオ会議ツールなどを活用できます。売却を進めるにあたっては、さまざまな情報を共有する必要があるので、状況に合わせてスムーズなコミュニケーション手段を検討しましょう。
話し合いを円滑に進めるために、あらかじめ情報を整理し、選択肢を分かりやすく提示できるように準備しておくことが大切です。例えば、事前に不動産会社に無料査定を依頼して物件の相場を調べ、見込まれる売却価格を明らかにしておくことも有効なアプローチ方法です。
また、売却には費用がかかるため、どのくらいのコストが発生するのかをシミュレーションしておくのも、トラブルを未然に防ぐコツと言えます。
ステップ2:必要書類を準備する
共有名義の不動産を売却する際は、以下の書類等を準備する必要があります。
- 登記識別情報通知書または登記済権利証
- 境界確認書、地積測量図(土地・戸建の場合)
- 共有名義者全員分の身分証明書、実印・印鑑証明書、住民票
- 委任状(代表者が手続きを進める場合)
■登記識別情報通知書または登記済権利証
登記識別情報通知書とは、12桁の英数字で構成された「登記識別情報」が記載された書面であり、不動産売却では本人確認などに使われます。2006年までは登記済権利証が用いられていたため、登記がそれ以前に行われていた場合は、交付されている登記済権利証となります。
なお、登記識別情報通知書の再発行はできません。紛失してしまった場合は、名義変更の際に「法務局による意思確認の事前通知」や「司法書士などの資格者による本人確認情報の提供」といった手続きが別途必要になるので注意しましょう。
■境界確認書・地積測量図
境界確認書や地積測量図は、土地の境界や面積、地番などを確認するための書類です。すでに境界の確定や地積の測量が行われている場合は、法務局を通じて取得することができます。
境界が未確定のまま売却を進めるとトラブルの原因になってしまう恐れがあるため、土地家屋調査士に依頼して境界確認と地積測量を行いましょう。
■共有名義者全員分の身分証明書、実印・印鑑証明書、住民票
不動産を売却には、共有者全員分の身分証や実印が必要になるため、準備に時間がかかる可能性があります。共有者には早めに連絡を取り、必要書類の漏れがないように徹底してもらうことが大切です。
■委任状
代表者が売却手続きを行う場合は、他の共有者からの委任状が必要です。委任状は、原則として委任をする本人が自署し、共有者全員の記名、押印が必要となります。
委任を受ける場合は、必要な書類や委任状の書き方なども案内しておくとよいでしょう。また、ご自身が委任状を作成し、他の共有者に委任することも可能です。
ステップ3:売却活動を進める
共有者の合意が得られ、必要書類が整えば、後は通常の不動産と同様の流れで売却を進められます。不動産の売却では、スムーズな取引を実現させるために、不動産会社と媒介契約を結ぶのが基本です。
不動産会社は売却活動をサポートしてくれるとともに、契約に関する仲立ちを行い、トラブルを未然に防ぐ重要な存在です。信頼できる不動産会社を見極め、納得のいく売却を目指しましょう。
買い手が見つかったら、不動産会社を通じて交渉を進め、売買契約を締結します。契約時など共有者全員の立ち会いが必要な場面もありますが、事前に委任状を受け取った代表者がいれば、代表者のみで済ませることも可能です。
ステップ4:収益を分配する
売却代金を受け取ったら、収益を分配する必要があります。そのため、売却にかかる費用負担(仲介手数料や各種税金など)についても、取り決めておくとよいでしょう。
なお、売却費用を代表者が立て替える場合は、収益分配のタイミングで精算してもらうのがスムーズです。
ステップ5:税金の申告と納付を済ませる
不動産を売却したときは、翌年の確定申告で譲渡所得として申告し、利益に応じた税金を納付しなければなりません。確定申告は、全共有者が個別で行わなければならないため、申告漏れには十分に注意しましょう。
ただし、売却代金から取得費や売却にかかった費用を差し引いて利益が出なかった場合は、原則として確定申告の必要はありません。
トラブルを避けて売却を進めるためのポイント

共有名義の不動産を売却する際は、トラブルを避けるためにしっかりと準備をし、計画的に手続きを進めることが大切です。最後に、売却をスムーズに進めるためのコツや注意点を整理しておきましょう。
相続の段階で共有物の分割を行う
まだ相続が完了していない段階であれば、不動産相続時に共有物を分割し、分かりやすく整理してしまうのが理想です。共有物を分割する代表的な方法としては、「換価分割」が挙げられます。
換価分割とは、不動産などを売却して得た売却金を分割する方法です。共有財産を現金化することで、シンプルに分けられるのがメリットです。
さらに、換価分割で相続財産が現金化されれば、代金を相続税の納付に充てることもできます。相続する土地や建物の運用方法が定まっていない場合は、早めに換価分割の可能性を検討してみるとよいでしょう。
また、共有物の分割には、1人が不動産を相続する代わりに、他の相続人が対価として金銭を受け取るという方法もあります。この方法は「代償分割」と呼ばれており、換価分割と同じように不動産の共有を避けられるのがポイントです。
例えば、「相続した住宅などに住みたい相続人がいる場合」や「不動産の具体的な運用方法を決めている相続人がいる場合」は、代償分割を選択するとよいでしょう。
所在等不明共有者の持分取得制度を活用する
先にも述べたように、共有名義の不動産を売るには、まず共有者全員の所在を明らかにしなければなりません。しかし、相続人が多い不動産では、すでに共有者の所在がつかめなくなってしまっているケースもあります。
名義人の所在が分からな場合は、「所在等不明共有者の持分取得制度」の利用を検討してみましょう。この制度は民法改正で2023年4月1日から施行されており、裁判所の判断によって、所在が分からない共有者の持分を他の共有者が取得できるという仕組みです。
この方法であれば、所在がわからない共有者がいるケースでも、売却手続きを進められる可能性があります。
代表者を決めておく
手続きの流れでも触れたように、共有名義の不動産をスムーズに売却するには、窓口として代表者を決めておくことがポイントです。特に遠方の共有者がいる場合は、重要事項説明や売買契約、代金決済などに全員が立ち会うのは現実的でないため、委任状を作成して代表者を設定するとよいでしょう。
また、権利が複雑化しているケースや、話し合いが難しそうなケースであれば、弁護士に相談して法的なサポートを受けることも大切です。弁護士であれば、「他の共有者と代理交渉してもらう」「面倒な手続きや書類作成を代行してもらう」「トラブルが発生したときに対処してもらう」といった幅広い支援が受けられます。
最低売却価格を話し合っておく
スムーズに売却を進めるためには、売り出し前に最低売却価格を決めておくことも大切です。いざ買い手が見つかってから共有者全員で話し合おうとすると、合意を得るのに時間がかかり、せっかくの機会を逃してしまうかもしれません。
円滑な意思決定を行うためにも、売却の合意を形成する際は、最低売却価格や売却時期の目安や期限も話し合っておくとよいでしょう。
居住中の場合はリースバックを検討する
共有名義の不動産売却が進まない原因として、「共有者の1人が居住中である」というケースもあります。この場合は、売却によって共有者の居住環境が変わってしまうので、合意のハードルは通常よりも高くなるでしょう。
そこで、共有者が居住中の不動産売却においては、「リースバック」という仕組みを検討してみるのも1つの方法です。リースバックとは企業や個人投資家に住宅を買い取ってもらったうえで、改めて賃貸借契約を結び、借主として引き続き居住する方法を指します。
所有権は不動産会社に移ってしまいますが、居住環境はそのまま維持しながら、売却によってまとまった現金を得られるのがメリットです。また、その他の共有者にとっても、共有持分をスムーズに現金化できるのは大きな利点となります。
ただし、リースバックには「通常の相場よりも安く取引される傾向がある」「家賃を支払わなければならない」「契約期間や家の使用方法を制限される可能性がある」など、重大なデメリットも存在します。共有者にリースバックを提案する際は、後々トラブルになることを防ぐためにも、こうしたデメリットまできちんと説明するなど、丁寧なアプローチが重要と言えるでしょう。
複雑な共有名義の不動産売却にはプロのサポートがおすすめ

共有名義の不動産の売却には、原則として共有者全員の合意を得る必要があります。ただし、自身の共有持分のみを単独で売却することは認められているため、売却の手続きが面倒であれば、他の共有者に買い取ってもらうのも1つの方法です。
近年は法改正が進んでおり、「土地の分筆は持分の過半数で行える」「所在が分からない共有者の持分を取得できる可能性がある」など、共有財産の処分を進めやすくなっている面はあります。共有名義の不動産売却には多様な選択肢があり、手続きも多いため、できるだけ早い段階で不動産会社に相談することをおすすめします。
プロによるサポートを受けられれば、書類の不備や手続きの抜け漏れなどがなくなり、トラブルを未然に防ぐことができます。住友不動産ステップは、全国に広く店舗を設けており、幅広いエリアで売却相談を受け付けています。
売りたい不動産の条件や売却事情に合わせて、きめ細やかなサポートを行っているので、共有名義の不動産売却をお考えの方はぜひご相談ください。
無料査定依頼・売却相談はこちらまとめ

今回は共有名義での不動産売却の方法や流れについてご紹介しました。ぜひ本記事を参考に不動産売却をご検討ください。
関連記事
他にも詳しく知りたい方は以下の記事も参考になります。
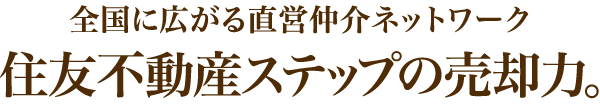
-
広告戦略からアフターフォローまで
マンツーマン営業体制 -

お問い合わせ時から、買主募集の広告戦略、ご契約、お引き渡し、アフターフォローまで、一貫した「マンツーマンの営業体制」により、お取引を責任を持って担当します。
-
地域に密着した営業ネットワーク
全国172営業センター -

全国に広がる172営業センターの地元に精通した営業担当者だからこそ、地域に密着したお取引を行うことが可能です。
※2026年1月1日時点
-
多彩なメディアを活用した
広告ネットワーク -

自社サイトの他、SUUMO・アットホームなど各種提携サイト※へ物件広告を行います。
※物件により掲載条件があります。
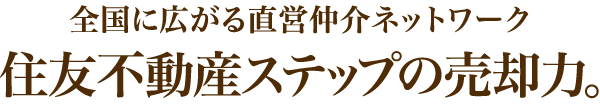
-
広告戦略からアフターフォローまで
マンツーマン営業体制 -
お問い合わせ時から、買主募集の広告戦略、ご契約、お引き渡し、アフターフォローまで、一貫した「マンツーマンの営業体制」により、お取引を責任を持ってご担当します。
-
地域に密着した営業ネットワーク
全国172営業センター -
全国に広がる172営業センターの地元に精通した営業担当者だからこそ、地域に密着したお取引を行うことが可能です。
※2026年1月1日時点
-
多彩なメディアを活用した
広告ネットワーク -
自社サイトの他、SUUMO・アットホームなど各種提携サイト※へ物件広告を行います。
※物件により掲載条件があります。
お気軽にご相談ください。
住み替えを検討している
税金や費用を知りたい
オークション形式の不動産売買をしたい
相続・空き地・空き家相談
売却・賃貸どちらが良い?
収益物件を組み替えたい
不動産売却お役立ちガイド
-
結婚、転勤、退職など、ライフステージの変化にあわせて住まいも変わるもの。その際に持ち家をどうすればよいかの不安や疑問にお答えします。
-
不動産取引の会話や文章によく出てくる専門用語を五十音順に掲載しました。辞書としてご活用ください。
-
住まいにまつわるさまざまな税金の知識を、身近なケースに即してわかりやすいQ&A形式でまとめました。初めての方にもわかりやすいよう、基本的な税制について紹介します。
-
ご所有のマンションなどを売却する際、売却検討や査定から引渡しまでの流れとポイントを説明します。
-
不動産売買時のよくあるご質問をQ&A形式でご紹介します。不動産売買について疑問がある方はこちらからご確認下さい。
-
はじめてマンションを売却する方は必見。売却までの流れの他、準備するべきポイントなどをご説明します。
-
一般の土地取引の指標ともなっている公示地価・基準地価を確認できます。(当社営業エリアのみ掲載)