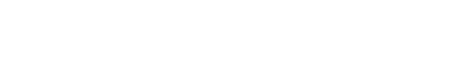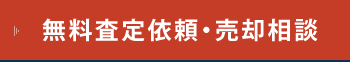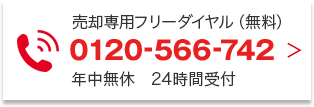相続した不動産の売却にかかる税金をまとめてチェック!節税につながる特例も解説
不動産売却に関する不安や疑問 更新日付:2025.8.10

2025年7月時点の情報及び税制に基づいて記載しております。
相続した不動産を売却するときには、具体的にどのような税金がかかるのでしょうか。この記事では、不動産を相続してから売却するまでにかかる税金を6種類に分け、それぞれの計算方法や課税のタイミングについて解説します。
また、相続した不動産を売却する際に活用できる節税方法も5つご紹介します。相続不動産の売却をご検討中の方は、この記事でぜひ税金の全体像を把握しておくことをおすすめします。
目次
【全体像を把握】不動産相続から売却までにかかる6種類の税金

不動産を相続してから売却するまでには、大きく分けて6種類の税金が発生します。ここではまず、6種類の税金の特徴を簡単に確認し、全体像を把握しておきましょう。
| 税金の種類 | 主な特徴 | 課税のタイミング | |
|---|---|---|---|
| 相続に関する税金 | 相続税 | 相続した財産の額に応じて発生 | 相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 |
| 登録免許税 | 登記の手続きを行う際に発生 | 相続後に所有権移転登記をするとき | |
| 売却に関する税金 | 印紙税 | 売買契約書などに貼る印紙代 | 買主との間で売買契約を交わすとき |
| 譲渡所得税 | 不動産の売却益に対して発生 | 売却した翌年の確定申告時 | |
| 住民税 | 不動産の売却益に対して発生 | 確定申告後(通常は6月ごろ) | |
| 復興特別所得税 | 不動産の売却益に対して発生 | 譲渡所得税に加算される | |
なお、不動産の登記移転手続きにあたって司法書士に代行を依頼したり、不動産売却で不動産会社に仲介を依頼したりする場合は、それぞれのサービス料(代行手数料や仲介手数料)に対して消費税がかかります。
特例を使えば一部税金が控除される
相続した不動産を売却する際は、さまざまな特例によって税金の一部が控除されます。例えば、代表的なのは「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」です。
これは、相続税の申告期限の翌日以降3年以内に売却すれば相続税のうち一定額を取得費に加え、譲渡所得から控除できるという仕組みです。また、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を使えば、譲渡所得から丸ごと3,000万円を差し引くことができ、大幅な減税につながる可能性があります。
特例については、利用条件などを最後に詳しくご紹介するので、ぜひご確認ください。ここからは、各税金の具体的な仕組みや計算方法について詳しく見ていきましょう。
相続税

相続税とは、被相続人(親など)から財産を受け継ぐ際に、その財産の価額に応じて納める必要がある税金です。しかし、相続税の計算にはいくつかの手順があり、算出した結果、税額がゼロになるというケースもめずらしくありません。
ここでは、相続税の基本的な計算方法や、課税(申告)のタイミングについて解説します。
相続税の計算方法
相続税の計算は、おおまかに以下の7つのステップで行います。
- 1. 遺産総額から非課税財産と葬式費用、債務を引く
- 2. 加算対象となる暦年課税にかかる贈与財産を足す
- 3. 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引いて課税遺産総額を割り出す
- 4. 課税遺産総額を法定相続分通りに取得したと仮定し、税率を適用して法定相続人別に税額を計算する
- 5. それぞれの税額を合計し、相続税の総額を求める
- 6. 相続税の総額を実際に取得された正味の遺産額の割合に応じて分ける
- 7. 各種の税額控除を差し引いて実際の税額を計算する
遺産総額とは、受け継いだ財産の総額のことです。生前に贈与を受け、「相続時精算課税制度」の適用を受けていた場合は、相続時にその総額も加算します。
なお、法定相続人の数は、相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の人数を指します。
その後、非課税財産(仏壇や墓、国や特定の公益法人への寄付、生命保険・死亡退職金の特定の範囲)と葬式費用、債務を引いて遺産額を割り出します。続いて、2つめのステップとして、「加算対象となる暦年課税にかかる贈与財産」(相続開始前7年以内に贈与されたもの)を加えます。
こうした求められた正味の遺産額から基礎控除額を引き、「課税遺産総額」を割り出すのが3つめのステップです。計算上、課税遺産総額については、まず法定相続分通りに分割されたと仮定して計算します。
その状態で、全法定相続人分の税額を一度バラバラに計算し、その後に再び合計します。そして、改めて実際に相続された割合に応じて税額を案分し、各相続人の負担額を算出するのが一連の流れです。
また、計算された税額には各種の税額控除が適用されます。この中で、特に重要となるのは、配偶者の税額軽減(配偶者控除)です。
配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者には相続税はかかりません。なお、配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要です。
相続税の申告期限
相続税の申告期限は、「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」です。また、相続税を金銭で納めるのが難しい場合は、土地などでの「物納」も認められており、物納や延納を希望する場合も相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に手続きをする必要があります。
なお、相続放棄をする場合は、「相続開始を知った日から3ヶ月以内」に手続きが必要なので、混同しないように注意しましょう。
登録免許税

登録免許税は、登記の手続きを行う際に発生する税金のことです。相続した不動産を売却する場合には、「相続後に所有権を移転する際」に登録免許税がかかり、登録手続きは義務化されています。
ここでは、基本的な計算方法や免税措置などについて詳しく見ていきましょう。
登録免許税の計算方法
不動産の所有権移転登記を行うときには、土地と建物のそれぞれについて手続きが必要です。相続による所有権の移転(相続登記)では、税率は土地も建物も不動産価額の0.4%となっており、売買による移転の2%よりも低く設定されています。
登録免許税の免税措置
土地の相続登記においては、一定の条件に該当する場合、登録免許税の免税措置を受けることができます。そのうちの一つが、相続した人が移転登記を受ける前に亡くなった場合に、新たな相続が生まれる際の1次登記の免税措置です。
例えば、親が祖父から土地を相続したときに所有権移転登記を行っておらず、そのまま亡くなり、新たに子に相続された場合について考えてみましょう。このケースでは、子が相続を受けた段階で、「祖父から親」「親から子」への2段階の移転手続きが必要となります。
しかし、令和9年(2027年)3月31日までは、このうち「祖父から親(1次相続)」に関する登記については、登録免許税が免除されることとなっています。そのため、未登記の土地を相続した方でも、費用を抑えて適切な手続きを行うことが可能です。
また、同じく令和9年(2027年)3月31日までは、少額の土地(価額100万円以下)の相続における免税措置も適用されます。
印紙税

印紙税とは、不動産売買契約を取り交わす際に発生する税金です。不動産を売却するときは、売買契約書を交わす際に売主・買主のそれぞれが印紙代を負担するのが通例です。
税額は取引金額によって異なり、不動産取引においては、令和9年(2027年)3月31日まで、以下の表のように軽減措置が適用されます。
| 契約金額 | 通常の税額 | 軽減後税額 |
|---|---|---|
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円超10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円超50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
国税庁『「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について』)
譲渡所得税

不動産を売却して売却益(譲渡所得)が出たときは、譲渡所得税・住民税・復興特別所得税が発生します。特に譲渡所得は、翌年の確定申告で自ら申告して納付する必要があるので、正しく計算できるようにしておきましょう。
譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税の計算方法はやや複雑であるため、ここでは大きく3つのステップに分けて解説します。
1.譲渡所得を計算する
譲渡所得は、以下の計算式で求めます。
譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)
まずは、「売却できた金額+固定資産税・都市計画税精算金」で譲渡収入金額を算出します。固定資産税・都市計画税精算金とは、年始に売主が支払った1年間の納付分から、引き渡し日から年末までの日数で日割り計算をし、買主に負担してもらう金額です。
その金額から、取得費と譲渡費用を差し引くことで、利益がどのくらい残っているのかを求めます。取得費とはその不動産を取得するための費用のことであり、具体的には次のようなものが含まれます。
取得費の例
- 土地や建物の購入代金
- 建物の建築費
- 設備費、改良費
- 購入時の印紙税、不動産取得税、登録免許税、登記費用
- 土地の造成費、測量費 など
建物の購入代金については、建物の種類や経過年数に応じた「減価償却費」を差し引かなければならない点に注意が必要です。また、相続した不動産については、被相続人の取得費がそのまま引き継がれるので、正確な情報を集めましょう。
なお、取得費が分からない場合は、「売却金額×5%」を概算取得費として用いることも可能です。続いて、譲渡費用とは、売却するためにかかった費用のことであり、次のようなものが含まれます。
譲渡費用の例
- 仲介手数料
- 印紙税(売主が負担したもの)
- 土地を売るために建物を取り壊した場合の解体費用や建物の損失額
- すでに売買契約を締結した不動産をより有利な条件で売るために支払った違約金
- 貸家を売るために支払った立ち退き料 など
このように、譲渡所得とは、売却できた金額から購入時・売却時の経費を差し引いたものであることが分かります。
2.課税譲渡所得を計算する
続いて、譲渡所得から特別控除を差し引き、課税譲渡所得(実際に課税対象となる譲渡所得)を求めます。相続した住宅・敷地・空き家を売る場合、令和9年12月31日までに売却し、一定の要件を満たしている場合は、譲渡所得から最大3,000万円までを控除することができます。
詳しい要件は後ほど解説しますが、適用されれば大幅な節税につながる重要な特例です。
3.所有期間に応じて税率をかける
最後に、課税譲渡所得に所有期間に応じた以下の税率をかけ、譲渡所得税を割り出します。
| 条件 | 税率 | |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 所有期間5年以下 | 30% |
| 長期譲渡所得 | 所有期間5年超 | 15% |
※所有期間の計算は、「売却した年の1月1日時点まで」の経過年数を対象とする。
短期と長期では税率が大きく異なるので、特に所有期間5年前後の不動産を売却する際は、タイミングに注意しましょう。なお、相続によって取得した不動産については、「被相続人の所有期間」を引き継ぐことができます。
「自身が相続してからではない」という点も正しく理解しておきましょう。
住民税

住民税も、譲渡所得税と同じように、課税譲渡所得に対して、所有期間に応じた税率をかけて求めます。
| 条件 | 税率 | |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 所有期間5年以下 | 9% |
| 長期譲渡所得 | 所有期間5年超 | 5% |
※所有期間の計算は、「売却した年の1月1日時点まで」の経過年数を対象とする。
住民税は確定申告の内容によって、売却した翌年の6月前後から徴収されます。給与所得者であれば、特別徴収として給与から天引きされるのが一般的です。
普通徴収(個人事業主など)の場合は、年4回の分納もしくは年間分の一括払いで納付します。
復興特別所得税

復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施する財源として、2037年までの所得税に加算される税金です。税率は基準所得税額の2.1%となっています。
譲渡所得税・住民税・復興特別所得税の税率を合計すると、不動産の売却益が出たときの税率は以下のように計算できます。
譲渡所得税・住民税・復興特別所得税を合計した税率
・短期譲渡所得:39.63%
・長期譲渡所得:20.315%
相続した不動産を売却するときに活用できる特例

相続した不動産を売却する際は、状況に応じて節税につながる特例を活用できるケースがあります。ここでは、5つの特例について詳しく見ていきましょう。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続した不動産を売却した際に、事前に納めた相続税も取得費として扱える特例です。取得費が増えることで、譲渡所得から差し引ける金額が増えるため、譲渡所得税の軽減につながります。
利用するための要件は以下のとおりです。
- 相続または遺贈により財産を取得した人であること
- その財産を取得した人に相続税が課税されていること
- その財産を、相続開始日の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却していること
このうち、特に重要なのは3つ目の条件です。相続税の申告期限の翌日から3年以内、つまり「相続開始を知ってから3年10ヶ月以内」に売却している必要があります。相続した土地や建物の売却も視野に入れている方は、売却価格だけでなく、タイミングにも注意することをおすすめします。
マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
マイホーム売却時に活用できる特例で、譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けられる制度のことです。控除額が大きいことから、マイホームの売却では、この特例によって譲渡所得税・住民税・復興特別所得税がゼロになるというケースも少なくありません。
相続した不動産についても、売却直前まで売主が自ら住んでいたのであれば、問題なく利用できます。ただし、相続後に売主が住んでいないとこの特例は利用できないため、注意が必要です。
主な利用条件は次のとおりです。
- 自らが住んでいる(あるいは以前に住んでおり、住まなくなってから3年を経過する日の属する12月31日までに売却する)
- 売却した年の前年・前々年に、この特例またはマイホームの譲渡損失について損益通算・繰越控除の特例の適用を受けていないこと
- 売却した年と前年・前々年にマイホームの買換えや交換の特例の適用を受けていないこと
- 親子や夫婦など「特別の関係がある人」に売ったものでないこと
基本的には特に問題なく利用できるケースが多いので、相続後に自身が居住していたことがある場合は、この特例の活用を検討してみましょう。
相続した空き家を譲渡する場合の3,000万円の特別控除
上記のように、自らが相続した不動産に住んでいない場合は、マイホームを譲渡する場合の特別控除は利用できません。しかし、空き家の状態であっても、一定の条件を満たせば、3,000万円の特別控除を適用できる可能性があります。
利用するための要件は以下のとおりです。
■不動産の主な要件
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられていること
- 区分所有建物登記がされていないこと
- 相続開始の直前に被相続人以外に居住していた人がいなかったこと
■その他の主な要件
- 売主が相続・遺贈を受けた人であること
- 一定の耐震基準を満たしていること、又は被相続人居住用家屋の全部を取り壊した敷地
- 相続から譲渡までに事業や貸付、居住のいずれの用途にも使われていないこと
- 売却代金が1億円以下であること など
上記の要件を踏まえると、この特例が利用できるケースは限定的と言えます。不動産の要件を満たしている場合は、売却のタイミングに注意しておくと良いでしょう。
10年以上所有していた場合の軽減税率の特例
売却する住居を10年以上所有していた場合、6,000万円以下の部分に対して、通常の長期譲渡所得税よりもさらに低い税率が適用される特例です。具体的には、6,000万円以下の部分の譲渡所得税の税率が、20.315%から14.21%(住民税・復興特別所得税含む)まで引き下げられます。
所有期間については、被相続人からのものが引き継がれるため、比較的利用しやすい特例と言えるでしょう。ただし、この特例を利用すると、一定期間にわたって「住宅ローン控除と併用できない」点に注意が必要です。
新居として住み始めた年と、その前後2年間の計5年間にこの特例を使っていると、住宅ローン控除が利用できなくなってしまうので、新たに住居の購入を検討している方は注意しましょう。なお、後述する「居住用不動産の買換え特例」とも併用できません。
特定のマイホーム(居住用不動産)の買換えの特例
特定の条件を満たした状態でマイホームの買換えを行う場合、売却時の譲渡益に対する課税を将来に繰り延べられるという特例です。相続した不動産に自ら住み、その不動産を売却して新たにマイホームを購入する場合は、次の新たなマイホームを売るときまで課税を先送りにすることができます。
ただし、この特例は売却日が令和7年(2025年)12月31日までの時限的な措置となっている点に注意が必要です。
税金の支払いタイミングと手続きの流れ

最後に、相続した不動産を売却する際に、どの税金をどのようなタイミングで支払うのか、手続き全体の流れとともにおさらいしておきましょう。
不動産を相続してから売るまでの手続きと税金
| 手続きの種類 | 期限・タイミング | 発生する税金 |
|---|---|---|
| 1.相続税申告手続き | 相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 | 相続税 |
| 2.相続登記手続き | 所有権の取得を知った日から3年以内 | 登録免許税 |
| 3.媒介契約 | 不動産会社に売却依頼を行うとき | なし |
| 4.不動産売買契約 | 買い手が見つかり、売買契約を結ぶとき | 印紙税、消費税 |
| 5.確定申告 | 売却した翌年の確定申告時(通常2月16日~3月15日) | 譲渡所得税・復興特別所得税 |
| 6.住民税納付 | 売却した翌年の6月前後 | 住民税 |
まずは相続税申告と相続登記手続きを済ませ、その後に不動産会社と媒介契約を結んで売却活動をスタートします。そして、買い手が見つかると不動産売買契約を結び、売却益が出たら確定申告を行って必要な税額を納付するというのが基本的な流れです。
媒介契約そのものは、相続手続きが完了する前から結ぶこともできるので、相続不動産の取り扱いに詳しい不動産会社に相談しながら手続きを進めるのも良いでしょう。
まとめ

相続した不動産を売却する際は、相続時と売却時の2つのステップに分けて税金の仕組みを把握しておく必要があります。相続時の税金は相続税と登録免許税であり、相続税には申告期限が設けられている点に注意しましょう。
また、売却時の税金は原則として負担しなければならないものと、売却益が出たときに発生するものの2種類があります。売却益の計算はやや複雑なので、ひとつずつ正確に手順をおさえていくことをおすすめします。
関連記事
他にも詳しく知りたい方は以下の記事も参考になります。
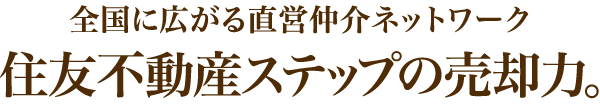
-
広告戦略からアフターフォローまで
マンツーマン営業体制 -

お問い合わせ時から、買主募集の広告戦略、ご契約、お引き渡し、アフターフォローまで、一貫した「マンツーマンの営業体制」により、お取引を責任を持って担当します。
-
地域に密着した営業ネットワーク
全国172営業センター -

全国に広がる172営業センターの地元に精通した営業担当者だからこそ、地域に密着したお取引を行うことが可能です。
※2026年1月1日時点
-
多彩なメディアを活用した
広告ネットワーク -

自社サイトの他、SUUMO・アットホームなど各種提携サイト※へ物件広告を行います。
※物件により掲載条件があります。
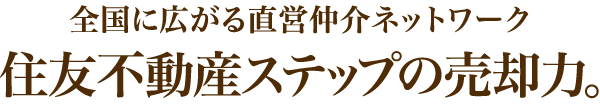
-
広告戦略からアフターフォローまで
マンツーマン営業体制 -
お問い合わせ時から、買主募集の広告戦略、ご契約、お引き渡し、アフターフォローまで、一貫した「マンツーマンの営業体制」により、お取引を責任を持ってご担当します。
-
地域に密着した営業ネットワーク
全国172営業センター -
全国に広がる172営業センターの地元に精通した営業担当者だからこそ、地域に密着したお取引を行うことが可能です。
※2026年1月1日時点
-
多彩なメディアを活用した
広告ネットワーク -
自社サイトの他、SUUMO・アットホームなど各種提携サイト※へ物件広告を行います。
※物件により掲載条件があります。
お気軽にご相談ください。
住み替えを検討している
税金や費用を知りたい
オークション形式の不動産売買をしたい
相続・空き地・空き家相談
売却・賃貸どちらが良い?
収益物件を組み替えたい
不動産売却お役立ちガイド
-
結婚、転勤、退職など、ライフステージの変化にあわせて住まいも変わるもの。その際に持ち家をどうすればよいかの不安や疑問にお答えします。
-
不動産取引の会話や文章によく出てくる専門用語を五十音順に掲載しました。辞書としてご活用ください。
-
住まいにまつわるさまざまな税金の知識を、身近なケースに即してわかりやすいQ&A形式でまとめました。初めての方にもわかりやすいよう、基本的な税制について紹介します。
-
ご所有のマンションなどを売却する際、売却検討や査定から引渡しまでの流れとポイントを説明します。
-
不動産売買時のよくあるご質問をQ&A形式でご紹介します。不動産売買について疑問がある方はこちらからご確認下さい。
-
はじめてマンションを売却する方は必見。売却までの流れの他、準備するべきポイントなどをご説明します。
-
一般の土地取引の指標ともなっている公示地価・基準地価を確認できます。(当社営業エリアのみ掲載)